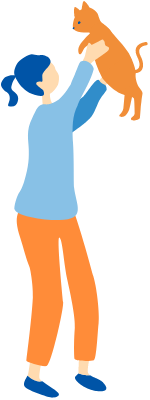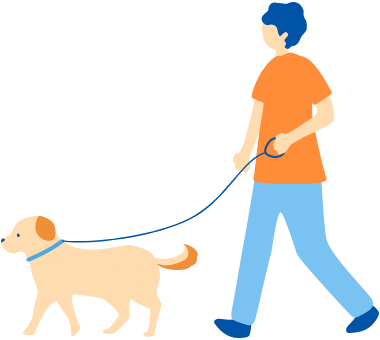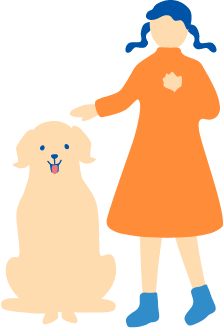
News
お知らせ・
求人情報
仔猫を保護する前に知って欲しいこと
【目次】
街角で小さな仔猫を見つけたとき、その愛らしい姿に心を奪われたり、衰弱した姿を見ると助けたい気持ちになる人は多いでしょう。仔猫を保護する経緯は様々だと思います。しかし、仔猫を保護することは、単なる一時の感情以上の責任を伴います。「仔猫を保護したので、どうしたらよいか?」「保護猫の診察の費用はどのくらいか?」といったお問い合わせもよくあります。
今回は、仔猫を保護する前に注意することや保護した際に最初にすべきこと、新しい家族として迎えるための注意点や準備についてや、動物病院で最初にかかる費用まで動物病院の視点から詳しくお伝えします。
仔猫を保護する前に
授乳中の母猫から仔猫を引き離さないで

仔猫を見かけても、親猫から離れている場合は親猫が戻ってくることがあります。母猫がエサを求めて仔猫のそばを離れているかもしれませんし、子育て中の猫は何度も引っ越しする習性があるため移動中かもしれません。人間を警戒して出てこないだけかもしれません。人間が仔猫を触ってしまった為に仔猫に人間の臭いがつくことで母猫が育児放棄をしてしまうケースもありますので、1日は様子を見てください。とくに離乳前の仔猫は母猫が授乳をして育てることが最善です。
保護する場合は命を預かる覚悟を!
もし、母猫が見当たらなかったり弱った仔猫を見た時には保護するかどうかを悩む場合があると思いますが、保護する場合は自身で最後まで命を預かる覚悟が出来るのかよく考えてください。自身で飼うか譲渡先を見つけるのかなど、保護した後のことも考えなくてはなりません。また、金銭的や時間の負担にも覚悟が必要です。怪我をしていたり、衰弱している場合は、手術や入院管理が必要となることがあります。様々な意見がありますが、保護しない選択をした場合でも間違いではありません。
仔猫を保護した直後にすべきこと
親猫が一向に見つからず、衰弱していくことが予想される仔猫をやむを得ず保護したとき、まず確認すべきはその状態です。仔猫が元気そうに見えても、隠れた健康問題がある場合があります。以下のステップを参考にしてください。
安全な場所へ移動
まずは安全な場所に移動させます。タオルや布で優しく包むと、仔猫も落ち着きやすくなります。また、屋外の動物はマダニやノミなどの寄生虫や皮膚糸状菌症やSFTS(※他のコラム参照)などの人獣共通感染症に罹患している可能性もありますので、先住の動物はもちろん、ご家族の方へ感染させないよう十分に注意する必要があります。特に、免疫力が未熟な乳幼児やご高齢な方、免疫疾患をお持ちの方は十分に気をつけてください。
体温や全身状態の確認
仔猫は未熟なため体温調節が不完全です。特に生後数週間の仔猫は、低体温症になりやすいため、暖かいタオルや湯たんぽ(低温で)で温めてあげましょう。暖かいお湯を入れたペットボトルにタオルを巻いて湯たんぽを作ることができます。湯たんぽが直接体に触れないよう、やけどに注意してください。
水分と栄養
仔猫が脱水状態に見える場合、少量の水をスポイトで与えます。ただし、固形物は胃腸に負担をかける可能性があるため、すぐに与えないでください。離乳前の仔猫には、専用のミルク(ペットショップや動物病院で購入可能)を与え、排泄の介助も必要です。牛乳は下痢を起こし、体力を消耗しますので与えないでください。

動物病院での診察
怪我をしていたり元気のない場合はなるべく早く受診することをおすすめします。あいづま動物病院では以下のような診察が行われます。
全身チェック
獣医師が仔猫の体重、体温、目や耳、口腔内の状態、皮膚や毛の健康をチェックします。ノミやダニ、皮膚病の有無も確認されます。必要な場合は糞便検査や血液検査、レントゲン検査なども行います。
年齢の推定
仔猫の歯や体の発達具合から、年齢を推定します。これにより、適切な食事やワクチンなどの予防のプログラムを考えます。
寄生虫検査
屋外で保護した猫は回虫やコクシジウムなどの内部寄生虫や、シラミや耳ダニ、マダニ、ノミなどの外部寄生虫に罹患していることもあります。全身のチェックや便検査を行い、必要に応じて駆虫薬を処方します。
感染症の検査
必要に応じて猫免疫不全ウイルス(FIV)や猫白血病ウイルス(FeLV)の検査を行います。これらは他の猫への感染リスクがあるため、ご自宅に先住猫がいる場合、早めの確認が重要です。しかし、幼少期では正確な結果が得られないことがあり、検査のタイミングに関しては獣医師とご相談ください。
鼻水や目ヤニ、くしゃみが出ている場合は猫かぜ(猫伝染性鼻気菅炎)の感染が疑われます。その場合、点鼻薬や目薬、あるいは飲み薬を処方します。
初期ワクチン
生後6〜8週以降の仔猫には、猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス、猫汎白血球減少症を予防する3種混合ワクチンが推奨されます。(当院では、迎え入れた1週間程度は無症状であったとしても何らかの感染症の潜伏期間の可能性もあるため、ワクチン接種をせず、経過観察を行います)
費用について
獣医師は仔猫の状態に応じて、適切な治療やケアのアドバイスを提供します。費用について心配や制限がある場合は、事前に獣医師やスタッフに相談してください。
費用は病院や地域により異なりますが、当院では初診料1500円(以下税抜き)、検査費用(3,000〜20,000円)、ワクチン(4,000〜8000円)ノミ、ダニなどの予防薬(1500〜3000円)が目安です。
通院治療が難しく入院治療になる場合、状態や治療内容によりますが1日あたり20000円前後が目安です。(特殊な処置、投薬、手術が必要な場合は獣医師から説明があります)
避妊・去勢手術の費用についてもよくお問い合わせいただきますが、目安は猫の事前の予防や術前検査なども含め50,000円〜100,000円程です。
※ 記載の費用はあいづま動物病院 (2025年5月現在)においての費用の目安です。各病院やその子の状態によって異なります。
仔猫の健康管理と自宅でのケア
動物病院での診察後、仔猫を自宅に連れて帰る準備を整えましょう。仔猫の健康を守るためには、以下のようなケアが必要です。
適切な食餌
仔猫用のフードを選び、年齢や体重に合わせて与えます。離乳前の生後4週未満の仔猫には、2〜3時間ごとにミルクを与える必要があります。過剰な給餌は下痢を引き起こすため、獣医師の指示に従いましょう。
清潔な環境
仔猫は免疫力が低いため、衛生管理が重要です。トイレは毎回掃除し、寝床は清潔に保ちます。ノミやダニがいる場合は、獣医師の推奨する駆除剤を使用してください。
社会化の開始
生後2〜7週は仔猫の社会化期です。優しく触ったり、さまざまな音や環境に慣れさせたりすることで、ストレスに強い猫に育ちます。ただし、過度な刺激は避けましょう。
仔猫期におすすめしたいコラムはこちらから「飼い主と猫が心身ともに快適に暮らすために 子猫期にすべきこと」
定期健診
ワクチンや駆虫のスケジュールに従い、定期的に動物病院を訪れます。生後6ヶ月頃には避妊・去勢手術を検討する時期です
新しい家族としての迎え入れ
仔猫を拾うことは、長期的な責任を伴います。以下のポイントを考慮し、準備を整えましょう。
家族の同意
同居人がいる場合、仔猫を飼うことについて全員の同意を得ることが重要です。アレルギーや生活スタイルも考慮しましょう。
費用
猫の飼育には、フード、トイレ用品、の他に医療費などがかかります。さらに、避妊・去勢の手術の費用も考慮しなくてはなりません。場合によっては、ブリーダーやペットショップで猫を迎えるよりも高額の費用がかかることがあります。
先住ペットとの相性
すでにペットがいる場合、仔猫との相性を慎重に確認する必要があります。徐々に慣れさせるために、別々の空間からスタートし、匂いや音を通じて慣らす方法が有効です。
まとめ
仔猫を保護したその後のケアや責任は決して軽いものではありません。動物病院での早期の診察と適切なケアを通じて、仔猫が健康で幸せな生活を送れるようサポートしましょう。愛情と知識を持って、新しい家族を迎える準備を整えてください。
あいづま動物病院では仔猫の譲渡先や保護団体の紹介は行っておりませんが、院内にお知らせの掲示や、SNSでの情報公開を行うことができます。また、仔猫のミルクのあげ方や排泄介助などお世話の仕方のアドバイスも行っております。お困りのときは、気軽にご相談ください。