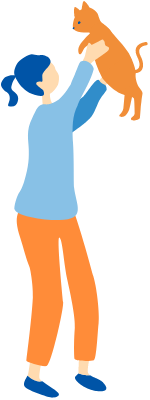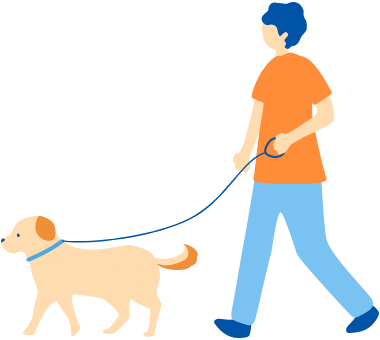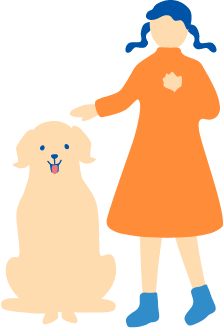
News
お知らせ・
求人情報
高齢猫としあわせに暮らすために知っておきたいこと
【目次】
近年、猫の世界も高齢化が進み、20歳を超える猫も珍しくなくなりました。これは、飼育環境の向上や獣医療の進歩によるものです。
人間同様、猫も歳を取れば出来なくなることや、不自由に感じることが増えてきます。そんな猫たちに、少しでも快適で健康な生活をさせてあげたい。そうした飼い主さんの声に応えるために、気をつける病気や生活のヒントをご紹介いたします。

「高齢猫」とは?
一般的に、猫は7歳から10歳くらいになると「シニア期」に入ると言われています。そして、11歳前後を「高齢期」、15歳以上を「超高齢期(ハイシニア期)」と区分することが多いです。人間でいうと、7歳は40代、11歳は60代、15歳は70代後半に相当するとされています。愛猫が高齢期に入るにつれ、その体は少しずつ変化していきます。この変化にいち早く気づき、適切なケアをすることが、愛猫の健康寿命を延ばす鍵となります。
高齢猫にみられる変化と病気
高齢猫に多くみられる体の変化や病気についてご紹介します。
被毛の変化
動くのが億劫(おっくう)になるシニア猫は、日に何度も行っていたグルーミングの回数が減ってしまいます。猫特有の体の柔軟性も失われていくため、体を大きく曲げないと届かない背中、後ろ肢、肛門などは特に手が回らなくなるようです。そのため、抜け毛が落ちず短毛種でも毛玉が出来てしまうこともあります。
爪が伸びたままになる
爪研ぎもあまり頻繁にしなくなるため、爪が伸びっぱなしになることがあります。放っておくと肉球に食い込んでしまうこともあります。
動作がゆっくりになる
シニアになると、猫は歩くのも、横になるのもゆっくりになります。今まで平気でジャンプしていた棚の上にも上がれなくなり、ときにはジャンプに失敗して落下することも。こうした変化は、筋力の衰えや関節の可動域の減少、体の機能の衰えによるものです。
性格が変わる
人間も歳をとると性格が丸くなったり反対に頑固になったりするように、動物にも歳を重ねたことによる心の変化がみられます。変化には色々なタイプがあります。
若い頃は撫でようとすると噛みつく仕草を見せたりする性格の荒い猫が、歳を取ると平気で人に撫でてもらったり、無反応になることがあります。
反対に、昔は撫でてもらうのが大好きだったのに、高齢になってからは、相手に怒ったりするようになる猫もいます。この場合は、体のどこかに痛みがあるのかもしれません。体の一部を触ると嫌がるようなときは、動物病院を受診しましょう。
異常な行動を取る
高齢になってから急に、飼い主さんの手や家具の脚などにひどく噛み付くようになった、さっきご飯をあげたばかりなのにすぐ催促する、同じところをふらふらと歩き回る、しょっちゅうトイレ以外の場所に粗相する…こんな行動がみられるようになったら、それは認知症(以前の痴呆症)かもしれません。
猫は犬に比べると、歳を取っても深刻な認知症の症状が現れる確率は低いと言われます。また、猫はもともとかなりマイペースな生き物なので、認知症の症状が出ても飼い主さんが気付かないことも多いようです。
高齢猫のかかりやすい病気
腎臓病
高齢猫に最も多い病気の一つが慢性腎臓病です。腎臓の機能が徐々に低下していく病気で、初期には症状がほとんど現れません。進行すると、多飲多尿(水をたくさん飲み、おしっこの量が増える)、食欲不振、体重減少、嘔吐などの症状に移行します。腎臓病は早期発見・早期治療が非常に重要です。定期的な健康診断(尿検査や血液検査)が重要です。
歯周病・口内炎
高齢になってくると次いで多いのは歯周病です。食欲が落ちるだけでなく、口臭が目立ってきた、よだれが増えてきた、フードを食べるときにガリガリ音がする、やたらと顔を洗う仕草が増えたなど、こういったサインは歯周病の兆候ですので注意が必要です。食欲が落ちると体重が落ち、脱水を引き起こし、全身状態が悪くなり他の疾患も併発してくるので、早めに対処する事が大切です。口内炎が重症化すると、全抜歯しなくてはいけない子もいます。
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。食欲が増えるのに体重が減る、落ち着きがなくなる、攻撃的になる、嘔吐や下痢などの症状がみられます。他の病気と症状が似ているため、気づきにくいことがあります。また、歳かな、加齢性の変化だろうと思っていても、実はこういった病気で治療をすれば改善することもあるのです。
関節炎
関節の軟骨がすり減り、痛みが生じる病気です。高い場所に飛び乗らなくなった、階段の昇り降りを嫌がる、歩き方がぎこちない、などの行動の変化がみられます。痛みから性格が穏やかでなくなることもあります。
心筋症
猫の心臓病の多くが、心室の壁が異常に肥大する肥大型心筋症です。軽症のうちは元気がない程度であまり症状がみられず、病気に気付かない飼い主さんがほとんどです。重症化してくると疲れやすくなって動かなくなり、咳や呼吸困難などの症状が表れます。猫は犬と違い口を開けて舌を出して呼吸することはほとんどありませんので、呼吸の仕方がおかしいなと思ったら早めに受診してください。また、悪化すると血栓症を引き起こし、急に後ろ足がおかしくなって歩けなくなった、なんて一見すると心臓とは関係なさそうな症状が実は心筋症の場合もあります。
がん・悪性腫瘍
高齢猫に多いのは、リンパ腫、乳癌、扁平上皮癌などです。嘔吐や下痢、食欲低下、体重減少などの症状がみられます。皮膚や皮膚の下のしこり、いつもと違う様子が見られたら早期に動物病院を受診しましょう。
快適なシニアライフのために出来ること
愛猫の老化のサインに気づき、快適な生活を送れるように環境を整えてあげることが大切です。
定期的な健康診断の重要性
高齢猫は、病気のサインを隠すのが得意です。飼い主さんが「少しおかしいな」と感じた時には、病気がかなり進行していることも少なくありません。そのため、見た目では元気そうに見えても、年に1回〜2回は健康診断を受けさせましょう。血液検査や尿検査、超音波検査などを定期的に行うことで、病気の早期発見につながります。
気をつけたい、シニアの食のあれこれ
高齢猫は、消化機能が衰えたり、食欲が落ちたりすることがあります。
・シニア向けフードを上手に活用しよう
高齢猫用のフードは、消化しやすく、腎臓に配慮した成分が含まれているものが多いので、切り替えを検討しましょう。
・水はしっかり飲ませよう
脱水症状を防ぐために、水分をしっかり摂らせる工夫も大切です。ウェットフードを混ぜる、水飲み場を増やし、常に新鮮な水を用意するなどの対策が有効です。
・食べやすくするための工夫
猫も歳を取ると足腰が衰えてきて、体を支えづらくなります。このため、床に置いた食器では食事が食べにくくなり、食が細くなる猫がいます。そういう場合は、猫が少しうつむくだけで食べられるように食器を台の上に乗せるなどしてあげるとよいでしょう。
また、フードを与える前に少し温めて香りを感じさせたり、食器の材質をガラスや陶器などいろいろ試してみるのもよいでしょう。

高齢猫が暮らしやすい環境を整える
高齢猫は、足腰が弱り、行動範囲が狭くなりがちです。
・ 段差をなくす
ソファやベッドに上がるためのスロープや階段を設置してあげましょう。
・トイレの場所
以前は問題なかったトイレの場所が、足腰が弱った猫には遠すぎるかもしれません。生活の中心となる場所にトイレを増設してあげましょう。ふちが低い、入りやすいタイプのトイレに替えるのも良いでしょう。
・安全な場所の確保
穏やかに過ごせる安心できる場所を用意してあげましょう。暖かく、人通りが少ない場所が理想的です。
・適切な温度管理
高齢猫は体温調整が苦手になります。夏は涼しく、冬は暖かく、室温を一定に保つように心がけましょう。
ボディケアでいきいき健康に
歳を取ると体の機能が衰えてくるのに加え、動くのが億劫になって、セルフグルーミングが十分に出来なくなります。ぜひ、飼い主さんが手伝ってあげてください。
被毛のお手入れは必須
感触のソフトなブラシを選び、頭からしっぽに向かってやさしくブラシをかけ、汚れや抜け毛を取り去ります。体を触ることで腫瘍などの異常も発見しやすくなります。
猫のブラッシングについてのコラムはこちらからhttps://aizuma-vet.com/news/p594/
爪は定期的にチェック
爪研ぎするのを面倒がるようになって爪が伸びすぎたり、爪が引っ込まなくなって出しっぱなしになるシニア猫もいます。爪の伸び具合は定期的にチェックして、伸びてきたらすぐに爪切りをしてあげましょう。
爪切りについてのコラムはこちらからhttps://aizuma-vet.com/news/p878/
まとめ
猫は、人に比べて歳をとっても見た目の変化が少なく、また行動の変化もあまりなく気づきにくいです。そのせいか、いつまでも「かわいいこども」のつもりでいてしまいます。しかし、実は猫の老化のスピードは人間よりもずっと早く、10歳前後から体にも行動にも老化のサインが表れてきます。
高齢猫のケアは、飼い主さん一人で抱え込むものではありません。少しでも気になること、不安なことがあれば、いつでもご相談ください。あいづま動物病院でも、飼い主様と猫の幸せな時間がずっと続いていくための一助となれるよう、サポート致します。私たちと一緒に、愛猫のシニアライフをより良いものにしていきましょう。