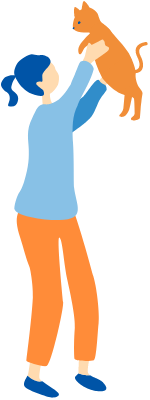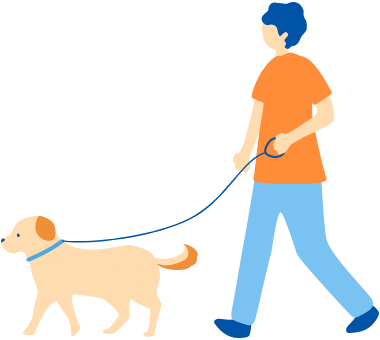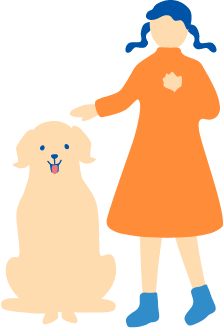
Preventive Medicine 予防医療

Vaccine 混合ワクチン
当院では、複数の病気を一度にまとめて予防することができる混合ワクチンを取り扱っています。ウイルスの感染によって生じる伝染病の中には、治療が難しく死亡率が高いものも存在します。
ドッグランや公園で遊ぶ時、トリミングサロンやホテルの利用時、車に乗せて外出する時など、動物たちが病原菌と接触する機会は少なくありません。目安として、子犬・子猫の場合は3~4週に2~3回、成犬・成猫の場合は年に1回ワクチンを接種し、動物たちの免疫力を高めておくことが大切です。
犬の混合ワクチンで
予防できる病気
-
ジステンパー
-
犬伝染性肝炎(A1)
-
犬伝染性喉頭気管炎(A2)
-
犬パラインフルエンザ
-
犬パルボウイルス感染症
-
犬コロナウイルス感染症
-
レプトスピラ感染症(イクテロヘモラジー・カニコーラ)
猫の混合ワクチンで
予防できる病気
-
猫汎白血球減少症(伝染性腸炎)
-
猫ウイルス性鼻気管炎(FVR)
-
猫カリシウイルス感染症
-
猫白血病ウイルス感染症
-
猫クラミジア感染症
その他、フェレットにはジステンパーワクチンの接種を行っています。
ワクチン接種に関する注意点
-
幼犬・幼猫のワクチン接種の開始時期・回数
幼犬・幼猫の場合は、1年に2~3回ほどワクチンを接種して確実に抗体を作ることが重要です。また、犬種・猫種によってワクチン接種を開始する時期や接種回数が異なるため、獣医師に相談しましょう。
ワクチンアレルギーがある子は、あらかじめお伝えください。
-
ワクチン接種後の過ごし方
ワクチンを接種した当日は激しい運動を控えて安静に過ごし、接種後3日間はシャンプーやトリミングを控えてください。また、体調に異変がある場合は当院までご連絡ください。
なお、継続的にワクチンを接種していない場合、ワクチン接種後、免疫ができるまでには2~3週間の期間が必要です。この期間はできるだけ他の動物との接触は避けてください。
海外渡航される方へ
動物たちを連れて海外渡航する場合、必要書類の作成や動物たちへのワクチン接種等を行っておりますので、ご希望の方は、お気軽に当院までご相談ください。なお、必要な書類や処置は渡航先の国によって異なりますので、飼い主様自身で渡航先の大使館等にお問い合わせの上ご確認ください。

Parasite フィラリアやノミ・マダニなど寄生虫の予防
当院では、フィラリアやノミ・マダニなどの寄生虫を予防・駆除できる薬を取り扱っています。錠剤タイプや注射タイプ、おやつタイプなど様々な種類を用意しており、動物たちの状態や予防したい病気の種類にあわせて処方しています。
薬の種類
- 錠剤タイプ
- 注射タイプ
- おやつタイプ
- スポットタイプ

Rabies 狂犬病の予防
当院では、狂犬病の予防接種を行っています。狂犬病ウイルスは犬だけでなく、猫や人を含む全ての哺乳類に感染する可能性があり、感染することで100%の確率で死に至る恐ろしい病気です。日本では狂犬病予防法に基づき、生後90日以上の犬に対して、お住まいの市町村に「登録」することと、年に一度「狂犬病の予防接種」を受けることが義務づけられています。
また、愛知県刈谷市・大府市・東浦町・知立市にお住まいの飼い主様の場合※、狂犬病の予防接種とあわせて鑑札(未登録の場合のみ)や注射済票、門標の交付等の手続きを受け付けています。
他の市町村にお住まいの場合は予防接種のみ対応しており、鑑札や注射済票等の手続きは飼い主様ご自身でお願いしております。

Neuter / Spay Surgery 避妊手術・去勢手術
避妊手術や去勢手術を行うことによって、乳腺腫瘍や卵巣腫瘍、精巣腫瘍、前立腺肥大などの病気を予防することができます。また、性ホルモンの分泌を抑え、発情に伴う出血やマーキング、噛み付く・唸るといった攻撃的な行動をある程度抑制することが期待できます。
当院では、生後7ヶ月ごろ(初回の発情前後の時期)で手術することを推奨していますが、犬種や猫種によって適切な手術時期が異なるほか、手術にはメリット・デメリットがあるため、手術を希望する飼い主様はあらかじめ当院の獣医師にご相談ください。
なお、ウサギやモルモット、ハリネズミ等の避妊手術・去勢手術にも対応しているため、ご希望の飼い主様はご相談ください。
子宮蓄膿症など、すでに症状が現れている場合は予防手術ではなく緊急疾患として対応します。
避妊手術・去勢手術によって予防できる主な病気
-
避妊手術の場合
- 乳腺腫瘍
- 卵巣腫瘍
- 子宮腫瘍
- 子宮蓄膿症
-
去勢手術の場合
- 精巣腫瘍
- 前立腺肥大
- 会陰
ヘルニア - 肛門
周囲腺腫
避妊手術・去勢手術の
メリット・デメリット
-
メリット Merit
- 望まない妊娠を予防できる
- 性ホルモンに関連した様々な病気を予防できる
- 発情に伴う出血(犬)や鳴き声(猫)の抑制が期待できる
- マーキング行動(犬)やスプレー行動(猫)の抑制が期待できる
マーキング行動やスプレー行動の抑制の効果には個体差があります。
-
デメリット Demerit
-
代謝が低下して体重が増加しやすくなる
手術後に獣医師より栄養指導を行っています。
-
手術の際に全身麻酔を行う必要がある
術前検査で動物の状態を把握するほか、複数の麻酔薬を組み合わせて使用することや心電図、呼吸モニター等で麻酔中も動物の状態を確認することで、麻酔事故の低減に努めています。
-
代謝が低下して体重が増加しやすくなる
手術に関する注意点
-
手術前の飲食
手術時に麻酔を使用するため、胃の中に食べ物が残っている場合は誤嚥性肺炎などが生じるリスクがあります。そのため、基本的には手術を行う前日の22時ごろから食餌を、当日の朝起床してからは食餌に加えて飲水も控えてください。
また、動物たちの種類や年齢、状態によって、飲食可能な時間や食餌が異なるため獣医師の指示に従いましょう。 -
体調・手術部位の確認
手術中に全身麻酔を使用するため、手術後もしばらくぼんやりした状態になることがあります。そのため、動物たちが安心できるよう、できるだけ静かな場所で安静に過ごすよう努めましょう。
また、手術後は定期的に手術部位を確認し、万が一、腫れや赤み、膿が見つかった場合はすぐに動物病院を受診して獣医師の診察を受けましょう。術後のケアは、動物の状態や性格、飼育環境によって異なるため、その子にあった対応について飼い主様と相談して決定しています。
避妊手術・去勢手術を受ける前に
手術を希望する場合は、あらかじめ血液検査等の術前検査を受ける必要があります。検査について、予約いただくことでスムーズに受診することができるため、詳しくは「ご予約・お問い合わせ」ページを確認ください。
さらに、ワクチンを接種していない動物の場合、まずはワクチンを接種し、1ヶ月経った後で手術を受けることが可能です。