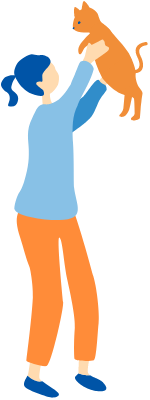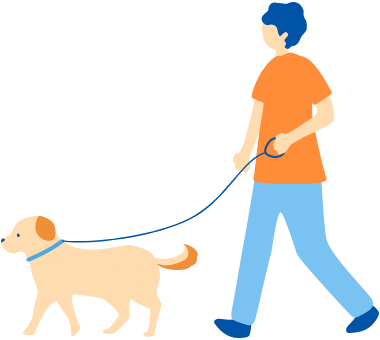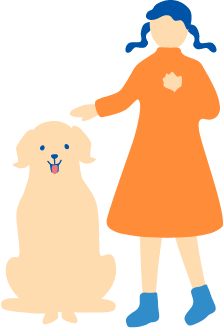
News
お知らせ・
求人情報
狂犬病予防注射について-正しい知識と副作用を知ろう
【目次】

犬を飼育しているご家庭にとっては狂犬病予防注射が義務づけられています。しかし、「なぜ毎年の接種が必要なのか」「副作用が不安」といった声もよく聞きます。幼齢や高齢であったり、病気の犬の接種を不安に思われる飼い主様もいらっしゃいます。また、小型犬と大型犬の接種するワクチンの量が同じことにも疑問に思われる飼い主様もみえます。そこで今回は、狂犬病や狂犬病ワクチンの正しい知識や重要性、副作用や副作用の対処法についてご説明します。
狂犬病の恐ろしさ
狂犬病とは
狂犬病は世界中で発生しており、多くの生命を脅かす深刻な病気です。人にも動物にも感染し、発症した場合は有効な治療法が存在せず100%の確率で死にいたる恐ろしい感染症で、潜伏期間は数週間から数ヶ月とされています。
日本における清浄国としての責任と、法的な義務
現在、世界で6地域のみが狂犬病の発生が報告されていないとされ、日本も1987年以降の発生が報告されていない国の1つで「狂犬病清浄国」に指定されています。
しかし、周囲国では依然として狂犬病が流行しており、狂犬病は稀な病気ではありません。ですから、狂犬病清浄国を維持し社会全体の安全を確保するため狂犬病予防注射が不可欠です。
日本では「狂犬病予防法」に基づき、全ての飼い犬に対して年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。これを怠ると、飼い主は20万円以下の罰金の対象となります。
人が感染した場合の治療と予防
海外、特に東南アジアなどで狂犬病が疑われる犬、猫、その他の野生動物に噛まれたり、ひっかかれたりした場合は、医療機関を受診し早期にワクチンや抗狂犬病ガンマグロブリンなどの投与を複数回受ける必要があります。ウイルスに感染している動物は症状が出る2週間前から唾液中にウイルスを排出し、感染させる可能性があります。日本では狂犬病が発生していないため、旅行等で海外に出かけても危険性を認識していない人が多くいます。潜伏期間に感染を特定する検査法はなく、一旦発症したら治療法がありません。人も必要があればあらかじめ予防法としてのワクチン接種することもあります。
狂犬病ワクチンについて
狂犬病ワクチンはどんなもの?
狂犬病ワクチンは「不活化ワクチン」という種類のワクチンです。増殖させた病原体を死滅させ感染力を失わせた後、免疫をつけるために必要な成分を取り出し作られます。副作用は起こりにくいと言われていますが、免疫を作る力が弱く、効果の発現が遅く、抗体の量が短期間で減っていくため定期的な接種が必要です。(ワクチンは大きく2種に分けられ「不活化ワクチン」と「生ワクチン」です。生ワクチンは生きた病原体を弱くしたワクチンです。)狂犬病ワクチンは狂犬病ウイルスをほぼ完全に防ぐことができ、無色透明の液体で多くの場合は首の後ろや腰に接種されます。
接種する量は体重に関係なく、1頭につき1mlと決まっています。なぜなら医薬品と異なり、ワクチンの用量は体重1kあたりのmgでは計算されておらず、効果的に免疫を刺激するには全抗原量が必要となっているからです。また、日本では1mlを接種しなければ狂犬病予防注射をしたとみなされません。
接種のタイミングについて
日本では生後91日以上の犬は、狂犬病予防注射を毎年1回受け、狂犬病予防注射後に注射済票の交付を受け犬に着ける決まりとなっています。飼育した時、すでに91日を超えている場合は30日以内に狂犬病予防注射をします。犬を飼ったら狂犬病予防注射の確認をし、未接種であれば適切な時期に迅速に接種してください。初回の接種では愛犬登録も同時に行い、鑑札も交付されます。引っ越しや犬の所有者が変わった場合も迅速に変更手続きを行ってください。2度目の接種からは、3月頃に犬の登録のお住まいの役所から予防接種のお知らせが届きます。
狂犬病予防注射は4月〜6月に打たなくてはいけないの?
4/1〜6/30の間に接種することが狂犬予防法にも記載されており、役所から届く狂犬病予防注射のお知らせにも同じ期間が設定されています。基本的には4/1〜6/30が推奨されますが、この時期を過ぎても接種は可能です。獣医師に相談し、必ず年1回の狂犬病予防接種を行いましょう。
※あいづま動物病院では毎年3/2から新年度の狂犬病予防注射を受け付けております。
料金について
狂犬病予防注射料 2950円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
愛犬登録料(初回のみ) 3000円
※あいづま動物病院では上記料金に加え、初診料もしくは再診料が必要です。
副作用と注意点について
狂犬病ワクチンの副作用は一般的に少なく、0.0006%とされています。接種部位の腫れや発熱など、軽度なもので数日以内に自然に解消されます。しかし、小型犬や幼齢犬や高齢犬では副作用の発現する確率がその他の犬よりも高くなります。接種後に、下痢や嘔吐、発熱、接種部位の痛みで足を上げたりなどの症状が出た場合は様子を見て、続くようであれば受診ください。また、呼吸が早くなったり、呼吸困難や痙攣発作やグッタリしている場合は病院へ連絡し、受診ください。
アナフィラキシー反応は接種後30分以内に発生することが多く、重い副作用も6時間以内に発生しやすいとされています。ワクチン接種後の様子をしっかり観察してあげることが重要です。万が一、副作用が出た場合の対処を考慮して午前中に接種することを推奨いたします。
幼齢犬のワクチン接種
幼齢の場合は初回の狂犬病予防注射は生後3ヶ月頃になります。体調や混合ワクチンとの接種時期を見て狂犬病予防接種を行います。
※当院では犬をご自宅にお迎えしてから、1週間の間隔を空けてからワクチン接種いただくようお願いしております。
高齢、病気の子のワクチン接種
狂犬病ワクチンの副作用は一般的に軽度であるため、基本的にはワクチン接種を行います。獣医師が狂犬病ワクチン接種の適応ではないと判断した場合は、「狂犬病予防猶予証明書」を発行し接種を免除することがあります。
ワクチン後の注意点
ワクチン接種後3日間はシャンプーを控えてください。狂犬病予防注射後に別のワクチン接種を受ける場合は、規定の日数を開ける必要があるため獣医師に確認してください。また、接種当日は安静に過ごし、犬の様子を観察してください。散歩は無理なく行ってください。
まとめ
今回は狂犬病予防接種について解説いたしました。狂犬病予防注射は愛犬の健康と安全、そして社会全体の公衆衛生を守るための重要な行為です。正しい知識を持って、義務を守り適切なタイミングで狂犬病予防接種することで愛犬と共に安心して暮らせる環境を作りましょう。
あいづま動物病院では刈谷市、大府市、知立市、東浦町の愛犬の鑑札・予防接種注射済票の交付が出来ます。その他の地域は、狂犬病予防注射時に証明書を発行いたしますのでお住まいの役所で鑑札・予防接種注射済票の交付の申請を行ってください。
また、当院では混合ワクチンとの同時接種は基本的には行っておりません。狂犬病予防注射の後に混合ワクチンを受ける場合は1週間の間隔を空け、混合ワクチンを先に受ける場合は1ヶ月の間隔を空けてください。不安な点や疑問がございましたら、お気軽に獣医師やスタッフにご相談ください。
あいづま動物病院は愛知県刈谷市で犬・猫・小動物の診療を行っています。動物たちの生活スタイルや体調に合わせてワクチンプログラムやノミ・マダニの予防をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。ご予約はお電話または予約ボタンからどうぞ。
参照
刈谷市ホームページ狂犬病予防接種 https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1008899/1003962.html
厚生労働省 狂犬病Q&Ahttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/07.html
世界小動物獣医師会ワクチネーションガイドラインhttps://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/WSAVA-vaccination-guidelines-2015-Japanese.pdf