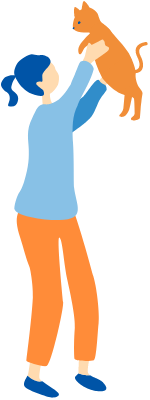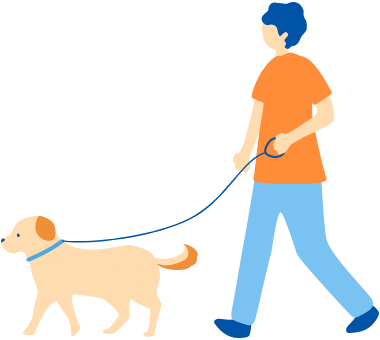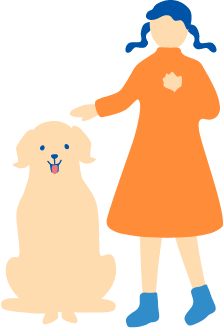
News
お知らせ・
求人情報
仔犬の健康を守ろう!ケンネルコフの基礎知識

今回は犬の飼い主様、特に新しく仔犬を迎えられた方々に知っておいていただきたい「ケンネルコフ」についてお話しします。ケンネルコフは、犬の「風邪」のような感染症で、正式には「犬伝染性気管支炎」と言います。咳が主な症状で軽症の場合が多いですが、特に免疫力が未熟な仔犬はかかりやすく、重症化することもあるため注意が必要です。実際当院でも飼い始めたばかりの仔犬の受診で多く見られる病気です。
今回は、原因、症状、感染経路、予防法を中心に、ご説明します。愛犬の健康を守る参考にしてください。
ケンネルコフとは?症状の特徴
ケンネルコフは、犬の呼吸器系に影響を及ぼす感染症です。初期は乾いた咳が多いですが、治療せず長期化、慢性化すると気管への分泌物により湿った咳になります。さらに悪化すると、分泌物が詰まったり気管壁が厚くなることで呼吸促拍、呼吸困難になることもあります。
症状は感染後3〜10日で現れ、1〜3週間続くことが多いです。特に、仔犬や高齢犬、持病のある犬では症状が重くなりやすいので、早めの対処が重要です。
原因と感染経路
ケンネルコフの原因は、複数の病原体による複合感染です。主なものは、細菌の「ボルデテラ・ブロンキセプチカ菌」と、ウイルスの「犬パラインフルエンザウイルス」「犬アデノウイルス2型」などです。これらが単独または組み合わさり気管や気管支を刺激し、炎症を引き起こします。感染力が高く、飛沫感染や直接接触で広がります。
犬の集団生活施設(ペットショップ、ブリーダー、シェルターやトレーニングスクール)でも流行しやすいため、「ケンネル(犬舎)コフ」と名付けられたほどです。
幼若犬はブリーダーやペットショップで集合飼育されているため、そこで感染していることがあります。特に、仔犬がかかりやすい理由は、免疫力が低いからです。生後2〜6ヶ月の仔犬は、母犬からの移行抗体が減少し、自分の免疫システムがまだ発達途上です。譲渡されると移動や環境の変化などのストレスがかかることで免疫力が下がり、ケンネルコフを発症します。実際、多くの仔犬がケンネルコフにかかるのはこうした移行期です。
人間には基本的にうつりませんが、感染犬に触れ汚染された手や服を通じて、間接的に他の犬へ感染を広げてしまう可能性もあります。
予防の鍵
ワクチンの効果
ケンネルコフの予防で最も効果的なのは、ワクチン接種です。犬の混合ワクチン(通常5種以上)には、ケンネルコフの主なウイルス(パラインフルエンザウイルス、アデノウイルス)が含まれています。これにより、感染リスクを大幅に低下させ、重症化を防げます。ただし、すべての病原体をカバーすることはできません。
日常対策
ワクチン以外では、日常の衛生管理が重要です。特に仔犬を迎えたばかりの時期は、不要な外出を控え、徐々に社会化を進めてください。栄養バランスの良い食事と十分な休息で免疫力を高めるのも効果的です。
ドッグランやペットホテルでの感染も見られますので、体調の変化に注意してください。
治療法と飼い主様の対応
もし症状が出たら、すぐに動物病院を受診してください。他の犬にうつしてしまう可能性もあるため、できれば受診前に動物病院へ連絡するとよいでしょう。また、動物病院に到着したら、車の中で待機するなどそれぞれの動物病院の指示に従ってください。診察は主に聴診や触診、検温を行いますが、状況により血液検査(炎症マーカーや白血球数の測定)、胸部レントゲン検査を行う場合もあります。診断は症状からの暫定診断になります。確定診断のために、細菌培養検査やウイルス抗体価検査を行うこともあります。
軽症の場合1~2週間程度で回復しますが、難治性の場合治療期間が長期化する場合もあります。また、食欲低下が著しかったり、呼吸困難により血中酸素飽和度が低下しているなど重症化の場合は、入院が必要になることもあります。
治療は対症療法が中心で、抗生物質や抗菌薬、咳止め、去痰薬などを投与します。さらに、ネブライゼーションを行う場合もあります。(ネブライゼーションとは薬液を霧化して吸入させることです。動物の場合じっと吸入してくれないので、半密室空間を霧状の薬で部屋を満たすことで吸入させます。)
食欲低下などで脱水が認められる場合、皮下補液(皮下点滴)を行います。
ケンネルコフの症状が出ている間はワクチン接種を控え、症状が落ち着いてからワクチン接種を行います。家庭では、安静を保ち、加湿器で空気を湿らせると咳が和らぎます。水分補給も忘れずに行ってください。
まとめ
ケンネルコフは、適切な治療で重症化を防げる病気です。特に飼い始めたばかりの仔犬の体調をよく観察し、咳などの症状がみられたら早めに受診して下さい。
また、ワクチンスケジュールを獣医師と相談し、ワクチンの抗体ができてから散歩やドッグランなど愛犬との外出をし楽みましょう。