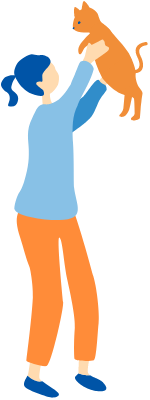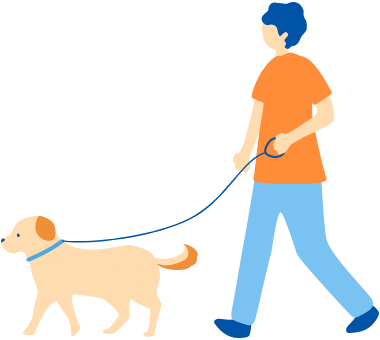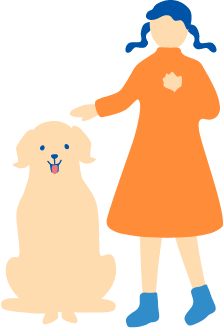
News
お知らせ・
求人情報
愛犬が人や犬を噛んでしまった時の対処法
【目次】

愛犬が人や他の犬を噛んでしまうことは、飼い主様にとって非常に心配で困惑する出来事です。当院でもそのような相談を時に受けることがあります。こうした状況は、愛犬の行動や環境、飼い主様の対応によってさまざまな要因で起こり得ます。「うちの子は絶対大丈夫!」ということはありません。今回は、愛犬が噛んでしまった場合の適切な対処法と、その後の予防策について、飼い主様向けに解説します。
噛んだ直後の対応
愛犬が人や他の犬を噛んでしまった場合、まず冷静になることが重要です。パニックになると状況が悪化する可能性があります。以下に具体的な対処手順を挙げます。
安全の確保
まず、愛犬をその場から速やかに離し、リードでしっかりとコントロールするか、必要に応じてケージや別の場所に移動させましょう。これにより、さらなるトラブルを防ぎます。興奮状態の愛犬が再び攻撃しないよう注意が必要です。大きな声で叫んだり、注意したりするとかえって興奮してしまうこともあるため、冷静な対応が求められます。
被害者への対応
人の場合
噛まれた人が怪我をしている場合、速やかに応急処置を行います。傷口を絞り出すようにして流水で念入りに洗ってください。
軽い傷であっても、なるべく早く医療機関での診察を受け手当てしてもらってください(動物病院では人に対しての診察や治療はできません!かかりつけ医や外科の先生に診てもらいましょう)。動物の咬傷は感染症のリスクがあるため、専門医の判断が重要です。 傷の程度によっては、薬の服用や、点滴や破傷風のワクチンも必要になります。
動物による咬傷は、噛まれた場所や細菌感染により、少しの傷でも酷く腫れたり発熱する場合があります。蜂窩織炎など重篤な感染症につながる場合がありますので、必ず医療機関を受診してください。
【人の医療費について】
また、他人の犬に噛まれた場合の医療費は加害者が負担するのが原則です。当人同士で話し合ってください。
原則として被害者側の保険証を使う場合は『第三者行為による傷病届』の提出が必要です。その場合は後日、負担額が加害者側へ健康保険や国民健康保険から請求されます。詳しくは受診された医療機関でご相談ください。(自身の飼い犬の場合はご自身の保険証が使用できます。)
犬の場合
ご自身の飼っている犬がよその犬を噛んでしまった場合、また、他人が飼っている犬にご自身の愛犬が噛まれてしまった場合、相手の飼い主様と連絡先を交換し、怪我の程度を確認するために獣医師の診察を提案しましょう。
誠意ある対応が、その後の関係を円滑に保つために大切です。
事実の記録
事件の詳細を記録しておくことをお勧めします。日時、場所、状況(何がきっかけで噛んだのか)、怪我の程度、目撃者の有無などをメモしてください。スマホやデジカメなどで被害状況を撮っておくことも重要でしょう。これらは後で保険会社や行政機関に報告する際に役立ちます。動物病院では怪我の受傷状況の診断書を作成することもできます。
行政機関への報告
日本では、犬が人を噛んだ場合は、まず動物愛護センターなど各自治体への報告(愛知県では48時間以内)と診断書の提出が義務付けられています。愛犬の狂犬病ワクチン接種状況を確認し、必要に応じて証明書を提示できるように準備してください。
診断書は動物病院にて愛犬が狂犬病にかかっていないことを証明する診断書(狂犬病鑑定書)を作成し、各自治体への提出します。動物病院では咬傷事故後すぐの診察と2週間後の診察の最低2回以上の診察を行い診断書を作成します。狂犬病の予防接種を行っている場合でも診断書の作成は必要です。
【愛知県では飼い犬事故届の提出が必要です。詳しくは以下HPから参考ください。】
飼い犬が人をかんだ、人が犬に噛まれた(愛知県HP動物愛護センター)https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/kandakamareta.html
飼い犬が人を噛んだ時の対処法(愛知県獣医師会)https://aichi-vet.or.jp/business-details/when-a-dog-bites-a-person.html
危害防止『犬が人をかんだら』(刈谷市)https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003965/1003969.html
原因の特定と再発防止
噛む行動には、恐怖、ストレス、興奮、縄張り意識、痛みなどさまざまな原因が考えられます。原因を特定することで、再発防止策を立てやすくなります。
専門家への相談
愛犬の行動に問題がある場合、獣医師やドッグトレーナー、動物行動学の専門家に相談することをお勧めします。ドッグトレーナーや専門家は、愛犬の行動パターンや環境を分析し、適切なトレーニング方法を提案してくれます。例えば、恐怖心から噛む場合は、徐々に社会化を進めるトレーニングが必要です動物病院では、行動改善のための指導や、薬やサプリメントによる行動療法の提案も行います。
ただし、これさえしておけば絶対大丈夫!というものはありませんので、特にやんちゃなわんちゃんは注意を怠らないことが常に飼い主に求められます。
健康状態のチェック
噛む行動が突然始まった場合、愛犬の健康状態に問題がある可能性があります。痛みや不調が原因で攻撃的になることがありますので、獣医師による健康診断を受けましょう。
環境の見直し
愛犬がストレスを感じる環境にいないか確認しましょう。散歩不足、過度な騒音、他のペットとの相性問題などが、攻撃性を引き起こすことがあります。十分な運動や精神的な刺激を提供し、安心できる環境を整えることが重要です。
飼い主様としての責任
愛犬が噛んでしまった場合、飼い主様には法的な責任が生じる可能性があります。民法では、動物の占有者はその動物が他人に損害を与えた場合、賠償責任を負うと定められています。以下に、責任ある飼い主として心がけるべきポイントを挙げます。
ペット保険等の確認
ペット保険などに加入している場合、咬傷事故が補償の対象となるか確認してください。保険が適用されれば、医療費や慰謝料の一部をカバーできる場合があります。
リードやマズルの使用
公共の場では、必ずリードを着用し、必要に応じてマズル(口輪)を使用しましょう。特に、愛犬が一度でも噛んだ経験がある場合は、再発防止のためにマズルの使用を検討してください。
伸縮リード(のびるリード)は瞬時のコントロールが難しくなりますので、注意が必要です。
社会化とトレーニングの継続
子犬の頃からの社会化トレーニングは、噛む行動を予防するのに重要です。しっかりとトレーニングを行い、さまざまな人や犬、環境に慣れさせることで、愛犬のストレス耐性を高めましょう。また、基本的なコマンド(「おすわり」「待て」など)を徹底することで、飼い主様のコントロールがしやすくなります。
獣医師としてのアドバイス
獣医師は、愛犬の健康だけでなく、行動面でのサポートも行っています。健康診断や行動評価を通じて、愛犬に最適なアプローチを提案します。行動療法の指導に加え、薬物療法や、歯の尖っている部分を削るなどの物理的な対策を講じることもあります。
また、来院時に他の来院動物や人との接触が不安な場合は事前にご相談下さい。

動物病院では行動療法や薬物療法に加え、犬がリラックスする効果があるフェロモン剤(ADAPTIL)などもご提案いたします。
最後に
小型犬だとしても、犬の噛む力は強く、咬傷事故は発生しております。また動物の瞬時の力は強く、小さなお子様ではコントロールできませんので注意してください。目を離した一瞬の隙に、肉体的にも精神的にも一生残るような深い傷を負わせてしまう恐れがあります。
愛犬が噛んでしまったことは、飼い主様にとって心の負担になるかもしれません。愛犬の行動は飼い主様の責任であり、愛犬を守れるのも飼い主様だけです。適切な対応と予防策を講じることで、愛犬との生活をより安全で楽しいものにしましょう。